こんにちは、コボオです。
FIREを目指すにあたって「節約は大事」と頭では分かっているのに、ついコンビニでスイーツを買ったり、気づけばサブスクが増えていたり…。そんな経験ありませんか?
実は、この「浪費してしまう行動」には心理学的な理由があります。今日は、20代が浪費から抜け出せない理由を心理学の視点から解説しつつ、克服法も紹介していきます。
1. ドーパミンの罠|小さな快楽に支配される
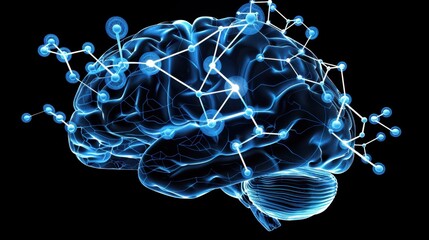
人は新しいものを手に入れると「ドーパミン」が分泌され、一時的な幸福感を得られます。
SNSでの「いいね」やコンビニスイーツ、ガチャ課金などがやめられないのは、この快感を脳が求め続けるからです。
✅ 対策
- 「買う」前にスマホのメモに欲しいものを書いて、一晩寝かせる
- 「買わない」ことで得られる未来のリターンを可視化する(例:投資額に換算)
2. 「みんな買ってるから」バンドワゴン効果
心理学では「バンドワゴン効果」と呼ばれ、多くの人がやっていることを正しいと感じてしまう現象です。
友達が最新iPhoneを買うと、自分も欲しくなるのはこのせい。
✅ 対策
- 「必要だから欲しいのか」「周りが持っているから欲しいのか」を紙に書き出す
- 自分軸の消費リストを作る(例:本、自己投資、スポーツ用品など)
3. サンクコスト効果|やめられない支出
「もう3か月払ったから今さらやめられない」
これはサンクコスト効果で、投じたお金や時間に引っ張られて合理的判断ができなくなる心理です。
ジム会員や使っていないサブスクをそのままにしてしまうのは典型例。
✅ 対策
- 「今から契約するなら払うか?」と問い直す
- 解約リマインダーをカレンダーに入れる
4. 未来を過小評価する「現在バイアス」
人は「将来より今の快楽を優先する」傾向があります。
「今、5,000円の焼肉」vs「将来、投資で1万円」なら、つい前者を選んでしまうのです。
✅ 対策
- 将来のリターンを具体化する(投資シミュレーションを活用)
- 積立NISAなど、自動で未来に回す仕組みを作る
まとめ|心理を知れば浪費は防げる
浪費をしてしまうのは「意志が弱いから」ではなく、脳の仕組みがそうさせているからです。
だからこそ、心理を理解し仕組みを整えることで、浪費を最小限にできます。
👉 関連記事:「自動で貯まる仕組みが最強だった件」
👉 参考リンク(外部):バンドワゴン効果とは
20代のうちに浪費をコントロールできれば、FIRE達成のスピードは格段に上がります。
次回は「具体的な支出カットの実例」を紹介していきますね!🔥

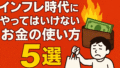

コメント